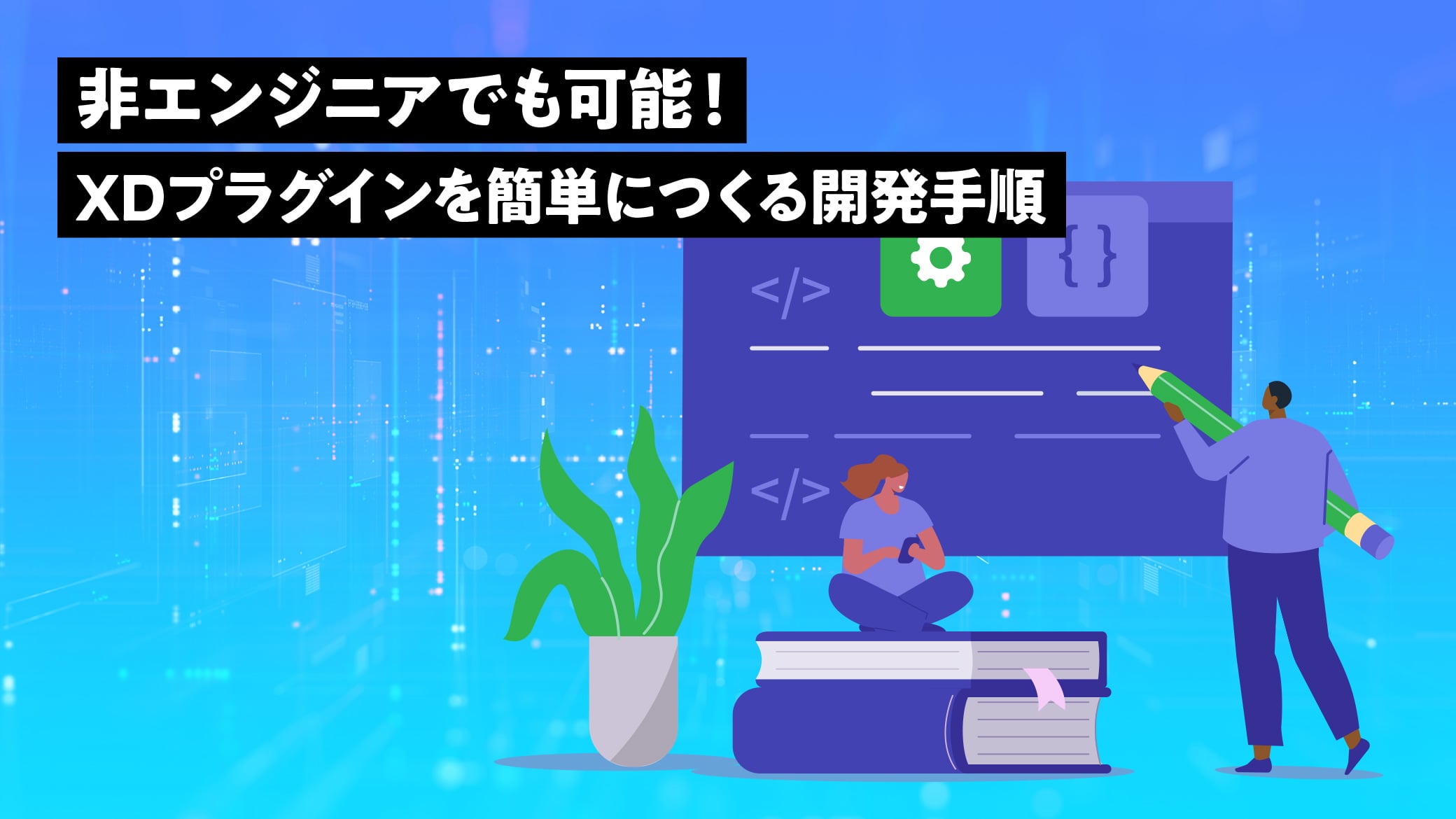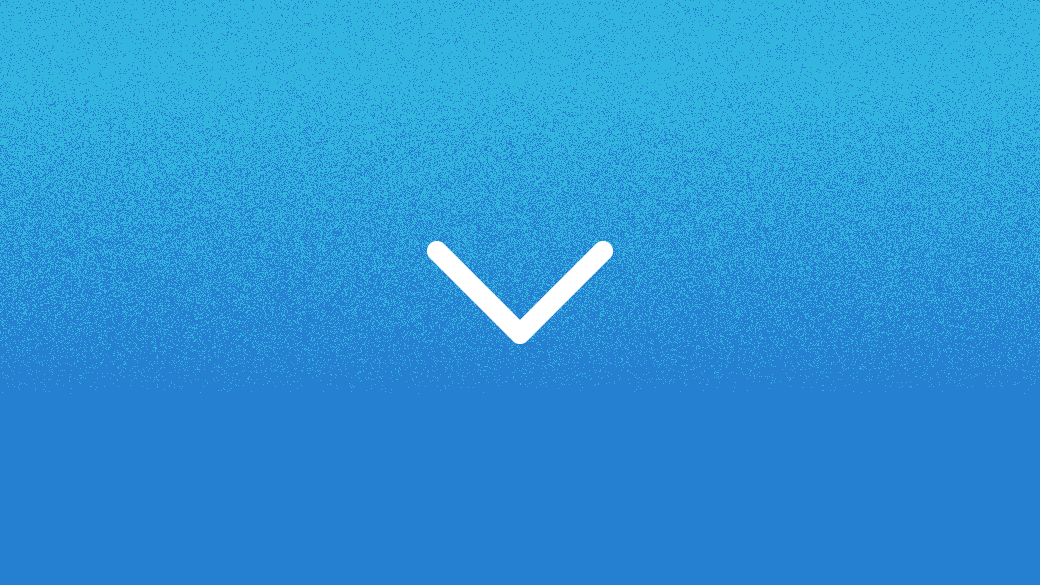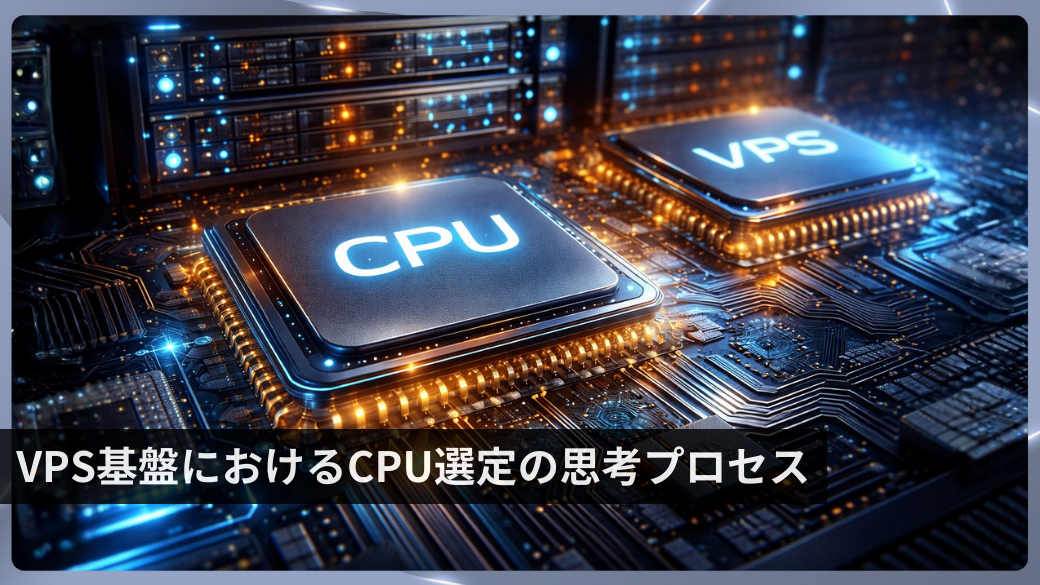こんにちは、デザイナーの板垣です。
現在はGMOでインハウスのデザイナーをしていますが、経歴としては制作会社で4社、28年にわたりクライアントワークのデザインを行ってきました。
現在の職場には、いわゆる「クライアント」と呼ばれる立場の人はいませんが、これまでのクライアントワークの経験をもとに、「クライアントがいる環境」で働くデザイナーの方々に向けて、よく耳にする「お客さま目線」とは何かについて、私なりの考えをお話しできればと思います。
目次
誰を「お客さま」と呼ぶのか
お客さま目線。
デザインをする人間であれば、誰もがものづくりをするうえで意識している言葉かと思います。
しかし、この言葉を錦の御旗のように掲げる前に、本当の意味を理解できているか、いま一度自分自身に問いかける必要があるのではないでしょうか。
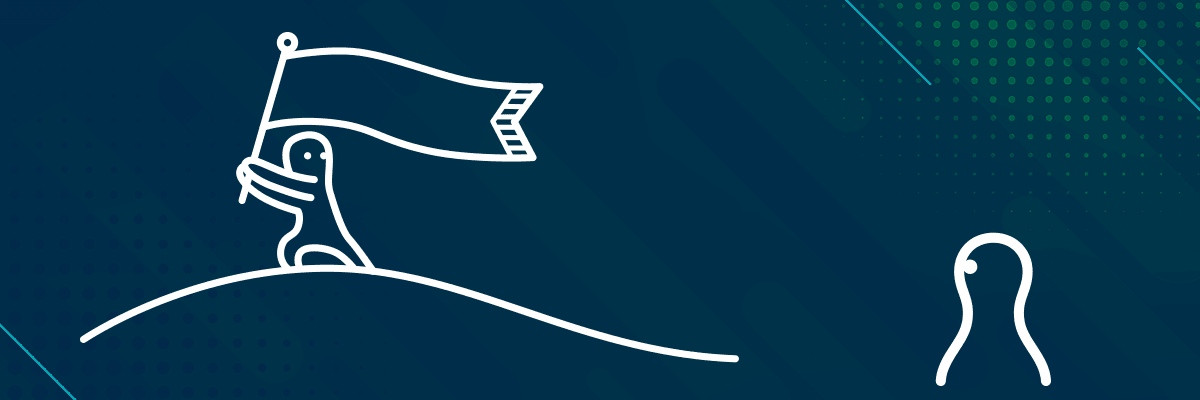
「お客さま目線で考えてほしい」
クライアントからのフィードバックにせよ、上長のチェックにせよ、よく聞く言葉です。
けれど、ここで言う「お客さま」とは誰のことでしょう?
・クライアントの担当者?
・そのクライアントの顧客であるエンドユーザー?
・あるいは、クライアント内の上司や決裁権を持つ別の関係者?
どの「お客さま」を優先するかで、制作物の設計は大きく変わります。
クライアント、あるいはその内部の決定権者のOKが出なければ、デザインは世に出ないかもしれません。
そのため、デザインのフォーカスがエンドユーザーではなく、自然とクライアントに向いてしまうことは往々にしてありうることです。
ターゲットは誰なのか。それを改めて見つめ直す際に重要なのは、「最終的に【行動】を起こすのは誰か?」を見極めることだと思います。
意思決定権者の確認を得ることはもちろん重要ですが、何より「最後に行動を起こす受け手」にフォーカスした設計が、本当の意味での「お客さま目線」に繋がります。
クライアントの要望 ≠ 真のニーズ
「バナーを赤に変えてください」という要望があったとしましょう。
具体的なフィードバックは、デザイナーとしては明快で助かります。
「よくわからないけどカッコよく」といった曖昧な指示に比べれば、ずっとやりやすいものです。
しかし、その要望は本当に「解決策」になっているでしょうか?
それは本当に“赤”が必要なのではなく、
・ユーザーの視線が集まっていない気がする
・競合と比べて弱く見える
・社内の会議で目立たないと指摘された
といった、背景的な課題があるのかもしれません。
重要なのは、その要望の奥にある「意図」や「本当の困りごと」は何かを掘り下げることです。
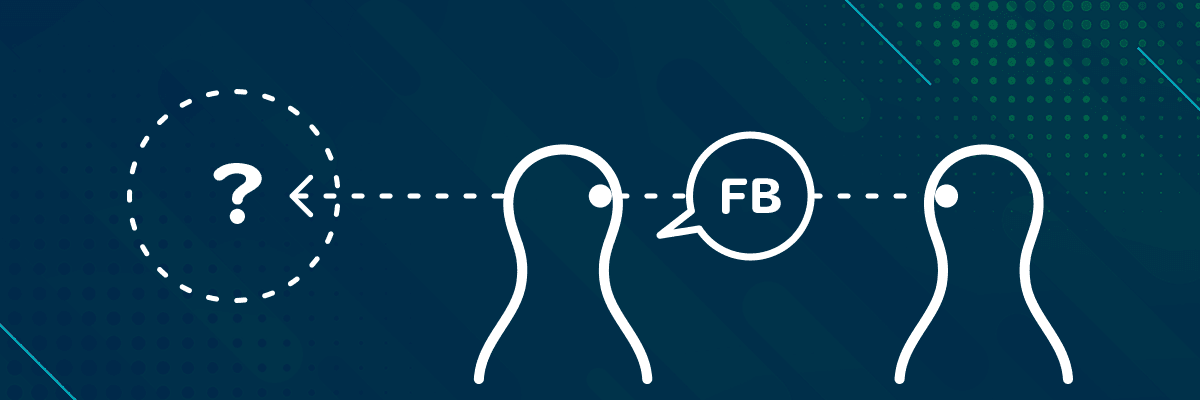
これを明らかにするには、以下のような問いかけが有効です。
・なぜこのタイミングでこの修正が必要になったのか?
・何を期待してこの要望を出しているのか?
・どんなユーザー行動や数値を想定しているのか?
こうして丁寧にヒアリングを重ねることで、「赤に変える」ことが解決策ではなく、「情報構造を見直す」「視線誘導の設計を調整する」といった、より本質的なアプローチが必要であることが分かることがあります。
指示の奥にある「なぜ?」を掘り下げていくと、真のニーズが見えてきます。
「お客さま目線」とは、指示をそのまま実行することではなく、真の課題を掘り起こして解決を目指す行為なのだと私は考えます。
エンドユーザーの視点を言語化する能力
「真の課題」は、エンドユーザーの立場になってみる「共感力」によって見つけることができます。
お客さまに共感することは、お客さまと同じ目線になること。
この「共感力」をフルに発揮することは、デザイナーに求められる重要なスキルのひとつです。
しかし、それだけでは足りません。
大切なのは、この共感力によって得た気付きを、適切に言語化することです。
曖昧なままにしてはいけません。
クライアント担当者の要望に対し、「いや、こうしたほうがいい」と別の視点を提案し、納得してもらう。
その際に、決定権者が担当者とは別にいるのであれば、実際にはその担当者に、決定権者への説明を任せなければなりません。
担当者とのMTGで、その場限りで「なんとなく」理解してもらっただけでは、担当者は上司にきちんと説明することができず、結局はもとの指示に差し戻されるかもしれません。
「その場しのぎの理解」ではなく、「要望をかみ砕き、なぜこの提案のほうが良いのかを明確に説明し、理解してもらう」。
この積み重ねがとても重要です。
そのためには、お客さま視点で得た気付きを「言語化できる力」が、何よりも必要です。
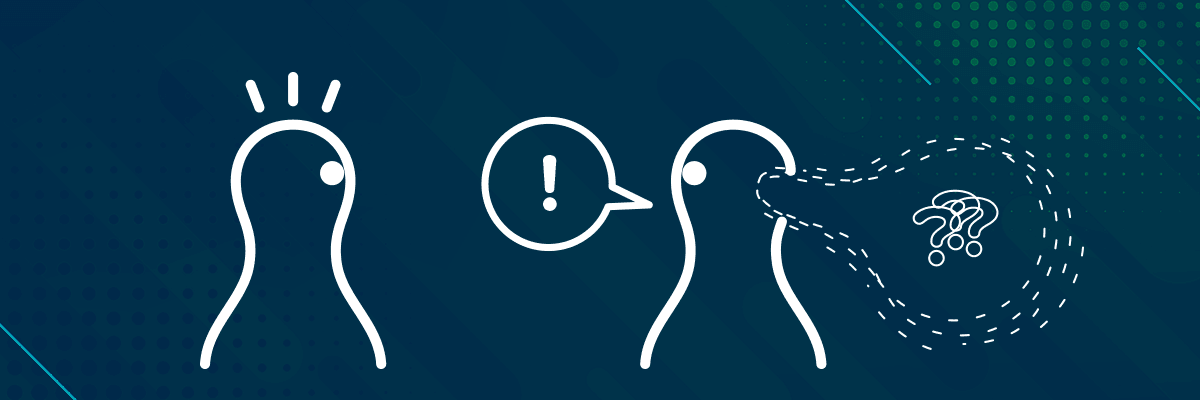
デザイナーはPCの前でゴリゴリ手を動かしていればよい、と考える人もいます。
しかし、デザイナーに本当に求められるのは、デザインそのものよりも、この言語化能力ではないでしょうか。
言語化できないということは、再現性のあるデザインができないということでもあります。
素晴らしいデザインが偶然に生まれることはあっても、それを説明できない、再現できないのであれば、次回も同じ結果になるとは限りません。
言語化スキルこそ、デザイナーにとって欠かせないメインスキルのひとつだと私は思います。
「ビジネス目線」と「お客さま目線」 ── 対立するようで、両立する視点
「その提案のほうがエンドユーザーにはウケがいいかもしれないけど……もっと商品をガンガン打ち出さないと魅力が伝わらないよ!」
クライアントから、こんな反応を受けることはよくあります。
特に「ビジネス目線」を重視するクライアントほど、商品やサービスを前面に押し出す訴求を求めがちです。
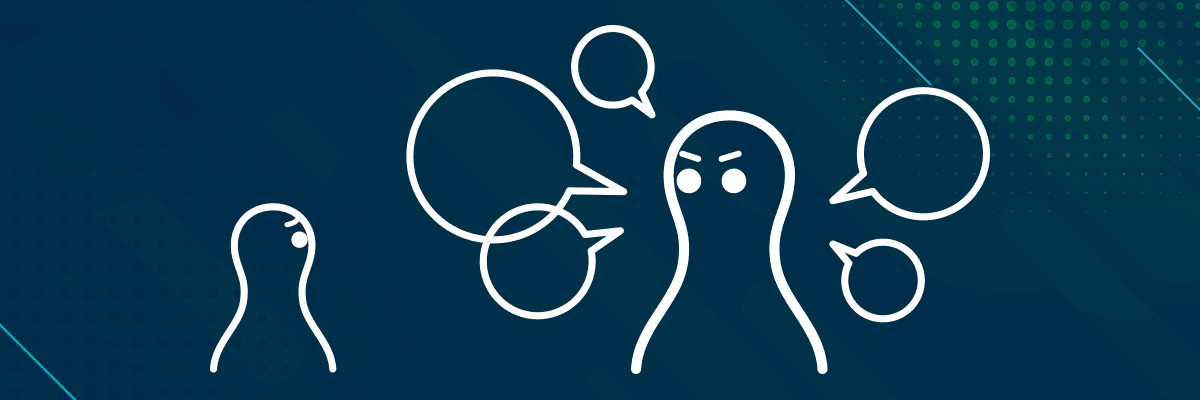
このとき、デザイナーはつい考えてしまいます。
「そんな押しつけがましいデザインは、今どきユーザーに嫌われるのでは?」
「もっと余白を活かして、視線誘導を丁寧に、ブランドイメージを大切にしたほうが……」
ですが、一度冷静になる必要があります。
そのデザインは、本当にそのターゲットのお客さまに合っているでしょうか?
例えば、おしゃれなカフェの広告と、ディスカウントスーパーのチラシでは、そもそもターゲットがまったく違います。
感度の高い層に刺さる洗練されたビジュアルが、価格を重視する層には「中身がよくわからない」「なんか高そう」と映ってしまうこともあります。
逆に、商品写真をぎっしり敷き詰めた“売り込み感満載”の広告は、落ち着いたブランドには不向きでも、買い物動機が「安さ」「量」「目玉商品」の層には、直球で届く表現だったりします。
つまり、「ビジネス目線」と「お客さま目線」は、一見対立するように見えて、実はそうではありません。
ターゲットによって、「どんなアプローチが喜ばれるか」「どんな表現が行動を促すか」はまったく違うのです。
重要なのは、「自分が好むか」「美しいか」ではなく、そのビジネスのターゲットとなるお客さまにとって最適なアプローチは何か?という視点を持つこと。
お客さま目線とは、「このユーザーにはこう響く」という理解であり、ビジネス目線とは「この層に買ってもらう」という意図。
両者は本来、矛盾せず、むしろ結びつくべきものです。
美しいクリエイティブが常に正解とは限らない。
逆に、泥臭いデザインが効果を発揮する場面もあります。
デザイナーはそこに「好み」や「常識」を持ち込まず、冷静にターゲットを見る必要があると、私は考えています。
目的を共有することが、目線を揃える第一歩
デザインの目的は、見た目を整えることでも、センスを披露することでもありません。
目的は、クライアントの課題を解決し、その先にいるユーザーに行動を起こしてもらうことです。
しかし、プロジェクトに関わる人が多くなればなるほど、その「目的」は曖昧になっていきがちです。
「売上を上げたい」「認知を広げたい」「ブランドイメージを向上させたい」……目的は何となく共有されているようでいて、具体的な行動や成果に落とし込まれていないケースが意外と多いと感じます。
だからこそ、デザイナーとして最初に確認すべきは、「この制作物は、誰に、何を、どうしてほしいのか」。
その目的がズレていれば、どんなに美しいデザインでも効果を発揮しません。逆に、その目的がきちんと合意できていれば、「ビジネス目線」と「お客さま目線」を両立させる判断基準ができるのです。
ターゲットは誰か。
そのターゲットは、何に困っていて、何を求めているのか。
この制作物は、その困りごとにどう役立つのか。
その結果、どんな行動を起こしてほしいのか。
これらを明文化してクライアントと共有できていれば、「赤にしたい」「もっと派手にしたい」といった要望が出てきたときも、「その目的に本当に必要か?」と冷静に立ち返ることができます。
目線がズレたまま走り出してしまうと、途中で必ず迷子になります。
だからこそ、目的の共有こそが、お互いの目線を揃える最初の一歩なのだと、私は思っています。
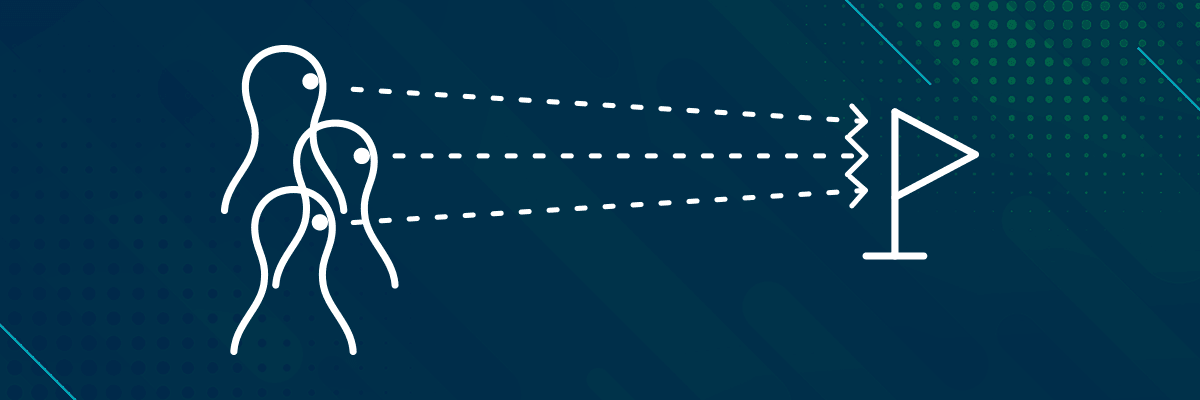
読者の呼吸をデザインするという視点
ここまで「お客さま目線」とは、課題解決の視点、行動を促す視点であると述べてきましたが、もうひとつ私が日頃から意識していることがあります。
それは、「読者の呼吸をデザインする」という視点です。
たとえば、この記事もそうですが、文章の書き方ひとつとっても、適切な場所で改行を入れるかどうかで、読み手の理解度は大きく変わります。
改行があることで、人は無意識に「一拍、呼吸を置く」ものです。
その一拍の呼吸が、そこまでに読んだ内容を整理し、次に進むための助走になります。
この小さな理解の積み重ねが、「読みやすい」「わかりやすい」と感じられる文章につながります。
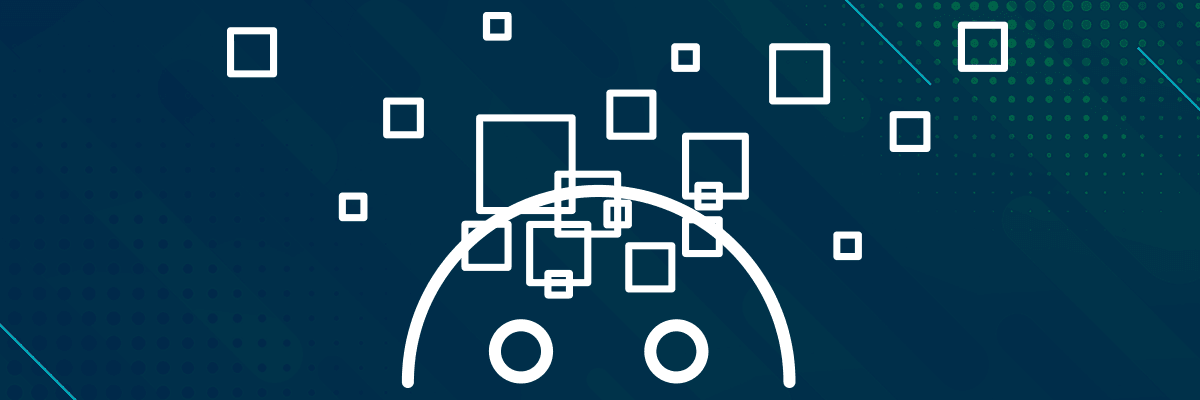
逆に、どんなに正しい内容でも、理路整然としていても、改行もなく詰め込まれた文章は「読みづらい」と感じられがちです。
疲れたときに読みたくない資料、最後まで読めないWebサイト……そういったデザインは、内容よりも先に呼吸が破綻していることが多いのです。
これはデザインでも同じです。
行間の取り方、余白の置き方、視線誘導のためのスペース。
それらは単に「キレイだから」ではなく、ユーザーがどこで一呼吸置くか、どこで頭を切り替えるか、どこで内容を整理するかという、無意識の行動をサポートする設計です。
内容が一字一句違わなくても、わかりやすさが大きく変わることがあります。
それは「呼吸」がデザインされているかどうかの差なのかもしれません。
サイト全体で決めたデザインのルールがあるとします。
このサイトのテキストは、句読点以外では改行しないルールになっているとします。
でも、内容を理解してもらうために、この単語で一拍置かせるために、あえて文章の途中で改行したい。
それが「ルールに抵触するから」という理由で避けるのだとしたら、守るべきはそのルールの方でしょうか?
読者の呼吸をないがしろにして守るべきルールなどない、と思っています。
だから私は、制作物を見るとき、自分がデザイナーであることを一度忘れます。
「初めて触れる人が、どこで呼吸を置き、どこで内容を整理し、どこでスムーズに行動へとつなげるのかが、コントロールされた設計になっているか」。
そうした視点でチェックするようにしています。
読み手、ユーザー、お客さま。
「お客さま目線」とは、そういった小さな呼吸の積み重ねにまで気を配る姿勢なのだと、私は考えています。
終わりに──「お客さま目線」は姿勢である
「お客さま目線」という言葉は便利です。
しかし、それが具体的に何をすることなのかを考えずに使ってしまえば、ただのスローガンで終わってしまいます。
私が考える「お客さま目線」とは、常に問い続ける姿勢です。
このデザインは、誰のためのものか。
この表現は、どんな行動を生み出すのか。
この案内は、迷わせず、気持ちよくゴールまで導けているか。
この文章は、どこで呼吸できるように設計されているか。
その問いを、何度でも自分に投げかけながらデザインをしていくこと。
それが本当の意味で「お客さま目線」であり、デザイナーに求められている仕事なのではないかと、私は思っています。
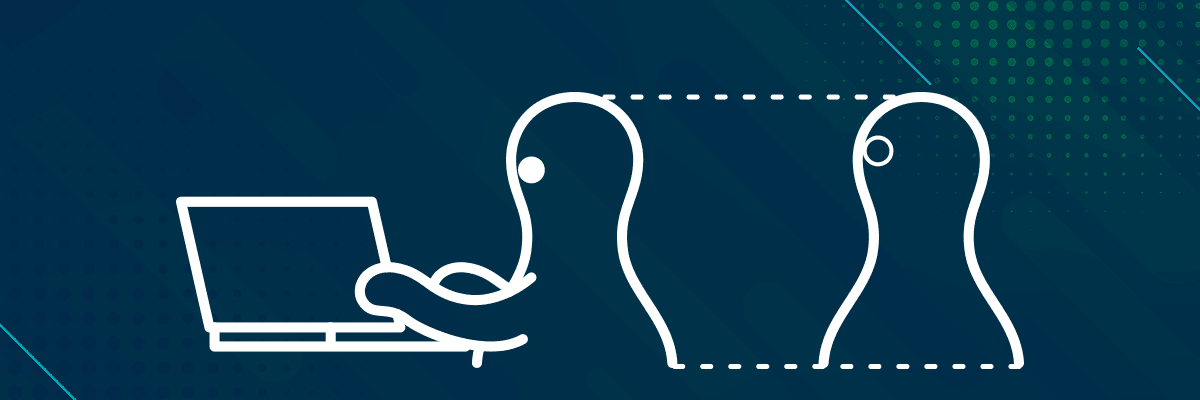
ブログの著者欄
採用情報
関連記事
KEYWORD
CATEGORY
-
技術情報(563)
-
イベント(210)
-
カルチャー(54)
-
デザイン(55)
-
インターンシップ(2)
TAG
- "eVTOL"
- "Japan Drone"
- "ロボティクス"
- "空飛ぶクルマ"
- 5G
- Adam byGMO
- AdventCalender
- AGI
- AI
- AI 機械学習強化学習
- AIエージェント
- AI人財
- AMD
- APT攻撃
- AWX
- BIT VALLEY
- Blade
- blockchain
- Canva
- ChatGPT
- ChatGPT Team
- Claude Team
- cloudflare
- cloudnative
- CloudStack
- CM
- CNDO
- CNDT
- CODEBLUE
- CODEGYM Academy
- ConoHa
- ConoHa、Dify
- CS
- CSS
- CTF
- DC
- design
- Designship
- Desiner
- DeveloperExper
- DeveloperExpert
- DevRel
- DevSecOpsThon
- DiceCTF
- Dify
- DNS
- Docker
- DTF
- Excel
- Expert
- Experts
- Felo
- GitLab
- GMO AIR
- GMO AIロボティクス大会議&表彰式
- GMO DESIGN AWARD
- GMO Developers Day
- GMO Developers Night
- GMO Developers ブログ
- GMO Flatt Security
- GMO GPUクラウド
- GMO Hacking Night
- GMO kitaQ
- GMO SONIC
- GMOアドパートナーズ
- GMOアドマーケティング
- GMOイエラエ
- GMOインターネット
- GMOインターネットグループ
- GMOクラウド]
- GMOグローバルサイン
- GMOコネクト
- GMOサイバーセキュリティbyイエラエ
- GMOサイバーセキュリティ大会議
- GMOサイバーセキュリティ大会議&表彰式
- GMOソリューションパートナー
- GMOデジキッズ
- GMOブランドセキュリティ
- GMOペイメントゲートウェイ
- GMOペパボ
- GMOメディア
- GMOリサーチ
- GMO大会議
- Go
- GPU
- GPUクラウド
- GTB
- Hardning
- Harvester
- HCI
- INCYBER Forum
- iOS
- IoT
- ISUCON
- JapanDrone
- Java
- JJUG
- K8s
- Kaigi on Rails
- Kids VALLEY
- KidsVALLEY
- Linux
- LLM
- MCP
- MetaMask
- MySQL
- NFT
- NVIDIA
- NW構成図
- NW設定
- Ollama
- OpenStack
- Perl
- perplexity
- PHP
- PHPcon
- PHPerKaigi
- PHPカンファレンス
- Python
- QUIC
- Rancher
- RPA
- Ruby
- Selenium
- Slack
- Slack活用
- Spectrum Tokyo Meetup
- splunk
- SRE
- sshd
- SSL
- Terraform
- TLS
- TypeScript
- UI/UX
- vibe
- VLAN
- VS Code
- Webアプリケーション
- WEBディレクター
- XSS
- アドベントカレンダー
- イベントレポート
- インターンシップ
- インハウス
- オブジェクト指向
- オンボーディング
- お名前.com
- カルチャー
- クリエイター
- クリエイティブ
- コーディング
- コンテナ
- サイバーセキュリティ
- サマーインターン
- システム研修
- スクラム
- スペシャリスト
- セキュリティ
- ソフトウェアテスト
- チームビルディング
- デザイナー
- デザイン
- テスト
- ドローン
- ネットのセキュリティもGMO
- ネットワーク
- ビジネス職
- ヒューマノイド
- ヒューマノイドロボット
- フィジカルAI
- プログラミング教育
- ブロックチェーン
- ベイズ統計学
- マイクロサービス
- マルチプレイ
- ミドルウェア
- モバイル
- ゆめみらいワーク
- リモートワーク
- レンタルサーバー
- ロボット
- 京大ミートアップ
- 人材派遣
- 出展レポート
- 動画
- 協賛レポート
- 基礎
- 多拠点開発
- 大学授業
- 宮崎オフィス
- 展示会
- 広告
- 強化学習
- 形
- 応用
- 情報伝達
- 技育プロジェクト
- 技術広報
- 技術書典
- 採用
- 採用サイトリニューアル
- 採用活動
- 新卒
- 新卒研修
- 日本科学未来館
- 映像
- 映像クリエイター
- 暗号
- 業務効率化
- 業務時間削減
- 機械学習
- 決済
- 物理暗号
- 生成AI
- 色
- 視覚暗号
- 開発生産性
- 開発生産性向上
- 階層ベイズ
- 高機能暗号
PICKUP