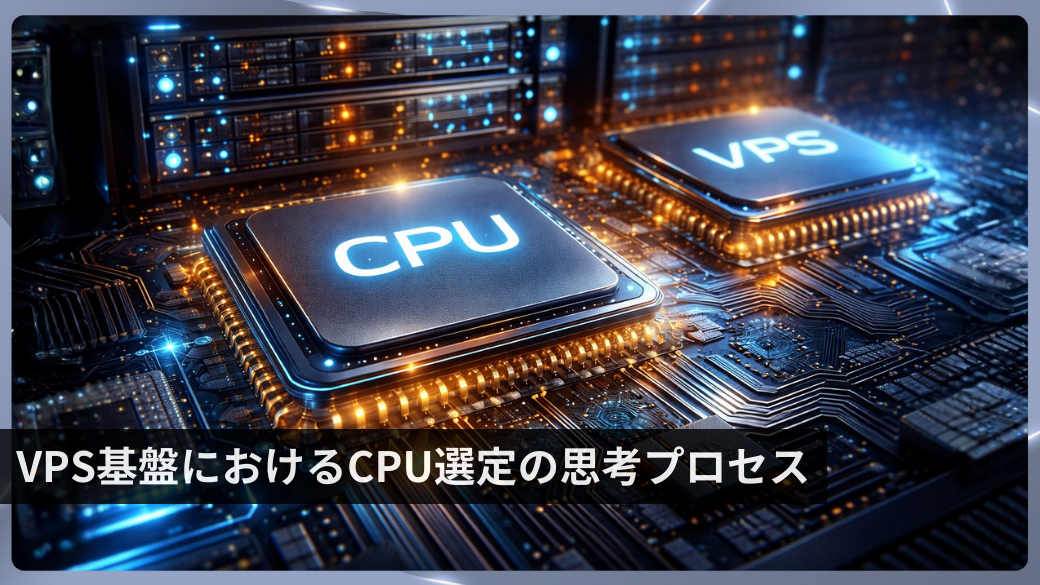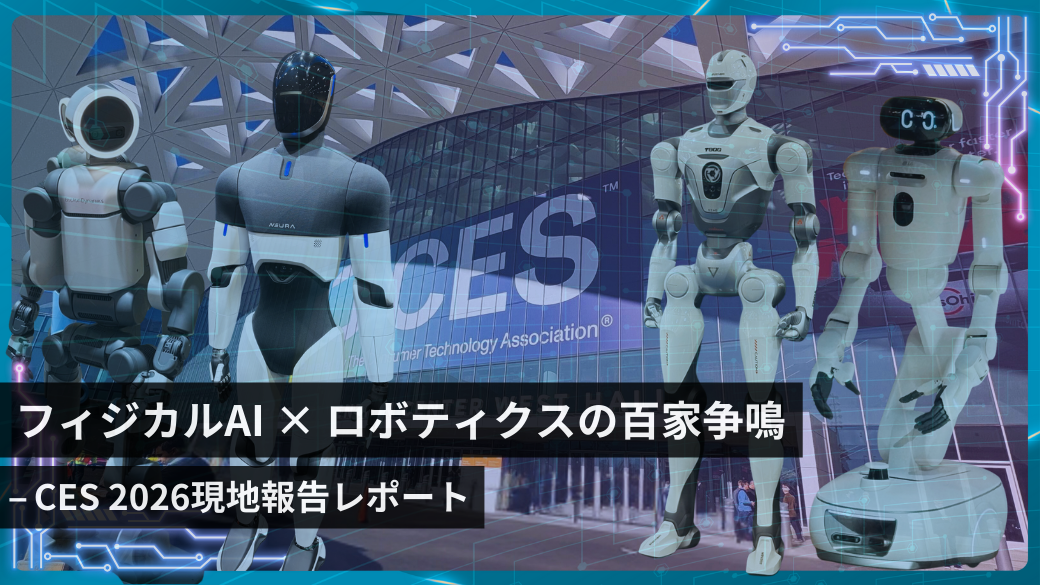※こちらはデザイナー・クリエイターインタビュー連載【後編】になります。
GMOインターネットグループが今年4月から開始した、年間を通してデザイン・クリエイティブの発信を強化する施策「Creator Synergy Project」の取り組みとして、本ブログでもデザイナー・クリエイターへのインタビュー連載をスタートしています!
[前編]デザインで組織を動かす。GMO全社横断クリエイティブ改革の始まりに続き、「クリエイターシナジー会議」会議の議長を務める近藤さん・現場実行の中核を担う岡本さんのお二人に、プロジェクトをどう動かし、仕組みとして定着させていったのかを掘り下げていきます。
目次
「UXチェックリスト」を共通言語に、全社を巻き込む
—GMOインターネットグループ全体への課題感が高まるなかで、社内的にはどのような取り組みが進められたのでしょうか?
岡本
着手したのは、「UXチェックリスト」でした。これは、各サービスのUXを点数化して評価するチェックシートで、GMOインターネットグループ内の各社に配布し、「この項目で○点以上を目指しましょう」とスコア管理する仕組みです。年末には進捗確認のタイミングも設け、全社的な取り組みとして展開しました。
背景には、やはりGMOインターネットグループ内における温度差がありました。会社ごとに事業ドメインや組織体制が異なり、デザイナーが常駐している会社もあれば、そもそもデザイナーがいない会社もある。そうした環境の違いは前提として、「最低限ここだけは押さえよう」という共通指針が必要だと感じたんです。

岡本 くる美|GMOメディア株式会社 サービスデザイン部 部長 / GMOインターネットグループ エキスパート(デザインマネジメント)
2014年に新卒でGMOメディアに入社。入社後はポイ活サイト「ポイントタウン」のデザイン業務全般を担当し、そのノウハウをもとにGMOリピータスの立ち上げに参画。約5年間にわたりリードデザイナーとしてポイントサイトの構築・運用に携わった。2021年からは横断型デザイン組織「サービスデザイン部」の責任者として、DesignOps全般を担いながら、採用活動やチームの技術支援、組織マネジメントなどに従事している。2025年4月よりGMOインターネットグループ エキスパートにも着任し、デザインマネジメント領域における広報活動や、グループ横断での組織づくりに貢献し活動の幅を広げている。
岡本
議論が始まったのは2023年の1〜2月頃。有志メンバーで週1回、毎回19時から夜な夜な集まって議論を重ねました。
悩んだのは、「理想をどこまで現実に落とし込むか」。あまりに高い水準を求めても現場は動けないし、かといって基準を下げすぎると意味がない。そのうえ、実行者が必ずしもデザイナーとは限らないため、「誰にでも伝わる内容」であることが求められました。
「この項目はわかりやすいかな?」「実行者がデザイナーじゃない場合もあるから、もっと噛み砕こう」といったやり取りを重ねながら、細部まで丁寧にすり合わせていきました。最終的に完成したのは、4〜5月頃だったと思います。
—曖昧になりやすいUXについて、客観的な指標を設けるのはかなり難しかったのでは。
岡本
その通りです。たとえば、最初に入れた項目のひとつが「デザイン組織があるかどうか」でした。私たちデザイナーにとっては自然な表現でも、非デザイナーの方には「“デザイン組織”って何?」「デザイナーが1人いればOKなの?」と伝わりにくかった。
また、レイアウトやビジュアルデザインに関する「整列」や「強弱」といった基本原則も、言葉だけではなかなか理解されづらい。そこで、「こういう状態が“整列”です」「これは“強弱”がない例です」といった図解を用意して、視覚的に補足しました。
さらに、「デザインプロセスが標準化され、文書化されているか」といった項目も、抽象的に受け取られがちな内容です。これも、「ワークフローにこうしたステップが含まれていて、それが明文化されている状態が“標準化”です」といった補足資料も整備しました。
チェックリストをつくるうえで、抽象度の高い項目については特に設計が難しかったですね。それでもなお、判断がぶれないように、可能な限りガイドラインを整備。「なんとなくの印象」ではなく明確な評価基準に沿って判断できるように設計しました。
GMO Developers Day 2023 岡本さん登壇セッション「デザイン横断組織PJの立ち上げから、PJで策定した「UXチェックリスト」について」
近藤
あれは本当に難しかったと思います。特にプロセスや仕組みに関する項目は、そもそも「チェックすらできない」状態の会社もありました。チェックリストはデザイナーだけで完結できるものではなく、組織全体の連携があって初めて機能するもの。やる気以前に、体制やリソースの問題で対応が難しい会社もあったと思います。

近藤 貞治|GMOインターネットグループ株式会社 グループ管理部門統括 グループクリエイティブ部 部長
GMO入社前はクリエイティブエージェンシーにてグラフィック・Webのデザイン制作に従事。インハウスでの経験を求め、2010年にGMOメイクショップへ入社。デザイン戦略部マネージャーとして、プロダクトやコミュニケーション領域のデザイン制作・管理を手がける。2019年にGMOインターネットグループへ転籍し、グループ全体のブランドマネジメント活動を担当し、全社横断のクリエイティブ強化プロジェクト「クリエイターシナジー会議」の議長も務める。
近藤
モチベーション上の課題もありました。いくら意義のある取り組みでも、現場からすると「今すぐ取り組むべき課題」とは見なされないこともあって。実際、提出期限ギリギリまで動きが見えない会社もありましたね。
岡本
それでもなんとか進められたのは、「担当役員を明確にした」からでしょうね。現場主導だけだと、どうしても優先順位が下がってしまいます。でも、役員案件となれば社内での注目度が一気に上がる。「どれだけ忙しくても後回しにはできない」と判断してもらえました。
ちなみに、このチェックリストが単なる評価ツールではなく、役員と現場が会話するきっかけ、いわば「コミュニケーションツール」としても活用されたのは、嬉しい誤算でしたね。
GMOインターネットグループの本気を社外に伝えていくために
—2023年は、対外的な発信強化やUXチェックリストの導入など、デザイン組織の基盤を整える年だったかと思います。これらを受けて、2024年にはどのような取り組みをされたのでしょうか?
岡本
2023年はさまざまな取り組みを行いましたが、内側の感覚としては「まだまだこれからだ」という気持ちが強かったです。大事な一歩ではあったものの、それだけでは採用にもつながりにくいし、「GMOインターネットグループが本気でクリエイティブに取り組んでいる」という姿勢が、外からはまだ見えていない。なんとかして“見せる場”をつくることが必要だよね、という話になったんです。
そこで動き出したのが、より外向けのプレゼンス強化。「認知拡大には、やはりイベントへのスポンサーシップが効果的なんじゃないか」ということで、国内最大級のデザインカンファレンス「Designship 2024」にトップスポンサーとして協賛・登壇しました。
[協賛レポート・前編]Designship 2024] /[協賛レポート・後編]Designship 2024


近藤
ああいう大きな取り組みができたのは、やっぱりGMOインターネットグループとしてのシナジーですよね。これまでは、どうしても「できる範囲のこと」にとどまっていたので。
岡本
そう思います。大きなイベントだっただけに、対外的なインパクトも大きかったですし。ブースに立っていたスタッフからは、「GMOって、こんなに幅広いサービスをデザインしているんですね!」といった声をたくさんいただいたと聞いています。GMOインターネットグループのデザイン力を社外にしっかり伝えられたと実感しました。
併せて各社のサービス紹介も行ったことで、「こんなにたくさんのサービスを展開しているんだ」と驚く声も多くいただいたようです。接触人数など、KPIとして設定していた目標も大幅に達成できて、定量的にも非常に良い成果が出たと思います。
近藤
イベント主催側からの反響も印象的でした。「GMOがこうした活動に本気で取り組んでいる」と認識されて、他のイベントの運営社からも、登壇などの声をかけていただけるようになったんです。まさに、“情報が流れ込むチャンネルが開いた”という感覚でしたね。
岡本
さらにこれと同時進行で、グループ初のデザインコンテスト「GMO DESIGN AWARD」にもチャレンジしました。これは社外、特に新卒や若手クリエイター層を意識した企画です。

近藤
ちょうどこの頃、GMOインターネットグループ全体でも「AI×ロボティクス」を重点領域に掲げた時期だったこともあり、「AI×笑顔と感動の創造」をテーマに、「AI×デザイン」に本気で向き合っていることを社外に向けて発信しました。GMOインターネットグループが次の時代にどう向かおうとしているのか、その一端を示す場にしたかったんです。
岡本
部門は「プロダクトアイデア」と「ビジュアル表現」の2つ。応募のハードルを下げるために「AIを活用していればOK」という条件にして、かなり間口を広く設計しました。学生部門も設けて、若手クリエイターが参加しやすいよう工夫しましたね。
賞金もかなり大きくて、最優秀賞は100万円、優秀賞は各40万円(最大4作品)、入賞は5万円。「GMOって面白いことをやっている会社なんだ」と思ってもらうための、長期的な関係づくりの入り口として企画しました。
「GMO DESIGN AWARD 2024」結果発表!最優秀賞は童話のIFストーリーを楽しめる「もしも童話」に決定


近藤
「GMO DESIGN AWARD」も、GMOインターネットグループのシナジーを強く感じた取り組みのひとつでしたよね。どうしても最初は遠慮が出てしまって、もう少し小規模な施策になるかなと思っていたのですが、「やるなら思い切って行こう」ということで、しっかり形にできたと思います。
「Designship 2024」も「GMO DESIGN AWARD」も、GMOインターネットグループとしての姿勢を外に打ち出せた、象徴的な出来事でした。
続けること、積み重ねること。その先に“ブランド”はできあがる
—少しずつ全社を巻き込みながら広がってきた「クリエイターシナジー会議」の取り組みですが、2025年以降はどのように展開していきたいと考えていますか?
近藤
ここまでの歩みは、確かに意義のある取り組みだったと思います。でも、僕たちにとってはまだ通過点。「デザイナーのプレゼンスを上げる」「GMOインターネットグループ全体のクリエイティブの質を底上げする」—この目標に対しては、まだまだこれからです。
ゆくゆくは、「GMOのデザイン、すごいよね」と自然に言われるくらいの存在感を目指して、いろんな手段を模索していきたいですね。
岡本
私は、まずは「続けること」が一番大事だと思っています。昨年の活動を、今年も、来年も、当たり前のように継続できる組織でありたい。
そして今度は、ようやくGMOのデザインに興味を持ってくれた人たちをがっかりさせないよう、プロダクト側の品質もしっかり提供していかなきゃいけない。ここまでやって初めてクリエイティブのブランド価値が高まっていくと思っています。
—お二人を見ていると、それだけのエネルギーがあるなら、デザイン会社を立ち上げたり、起業したりもできそうだと感じます。あえて「組織」にいる理由は?
近藤
個人的な話をすると、もともと制作会社にいた頃から「デザインの力で社会にインパクトを与えたい」という気持ちが強くて、インハウスに転向したんです。
そして今、GMOインターネットグループというスケールの大きな環境の中で、まさに「より多くの人に影響を与えられている」と実感しています。この規模感と裁量を、他の組織で得るのはなかなか難しい。だからこそ、ここで挑戦することに意味があると感じています。
岡本
私も近い感覚です。個人で何かを立ち上げたとしても、ここまでのスケールでの結果はなかなか生み出せません。GMOインターネットグループという企業資源を使って、より大きなインパクトを生み出せることが、私にとってすごく面白いんです。
近藤
本当に、「ただデザインしているだけじゃ得られない経験」がたくさんありますよね。苦労も多いですが、それも含めて面白い。
—説得力のあるお言葉です。そんなお二人が、今一緒に活動している仲間たちに期待することは何でしょうか。
岡本
この取り組みを、“追い風”として前向きに楽しんでもらえたらと思っています。最初から「GMOインターネットグループ全体を盛り上げたい」といった大義名分がなくても構いません。結果的に参加するメンバーが増え、活動自体が自然と広がっていけば十分です。「この活動に関わっておいたほうが、自分たちや自社にとってプラスになりそうだな」といった、ある種の打算的な動機でもまったく問題ないと思います(笑)。
近藤
まさに、そこがポイントですよね。「デザイナーの力を見せてやるぞ」くらいの気持ちで関わってくれる人が増えたら、きっともっと面白くなっていく。その熱やうねりが、所属している会社だけでなく、GMOインターネットグループ全体にも変化をもたらしていくはずです。
少し大きな話になりますが、GMOインターネットグループのブランドは、まだまだ構築フェーズです。
でも、だからこそ「今」が一番面白いタイミングなんじゃないかと。この瞬間に「ブランドを一緒につくっていける」というのは、個人のキャリアにとっても大きなプラスになるはずです。これからが一番楽しい!そんな気持ちで、ぜひ一緒にやっていきましょう。
岡本
GMOインターネットグループ全体は非常に大きな組織ですが、各社は中小企業のようなフットワークの軽さがあり、個人の裁量も大きいところも多いです。つまり、「いいとこ取り」ができる環境なんですよね。
さまざまな事業ドメインの中で、価値観の異なる人たちと出会い、協働できるのも、この環境ならではです。
近藤さんもおっしゃったとおり、GMOインターネットグループにはまだまだこれからの余地が残されています。でも、だからこそ「デザインの力で組織や社会を動かしていきたい」という想いを持つ人にとって、これ以上ないフィールドだと思います。一緒に挑戦できる日を、楽しみにしています。

インタビュー前編はこちらから
デザインで組織を動かす。GMO全社横断クリエイティブ改革の始まり
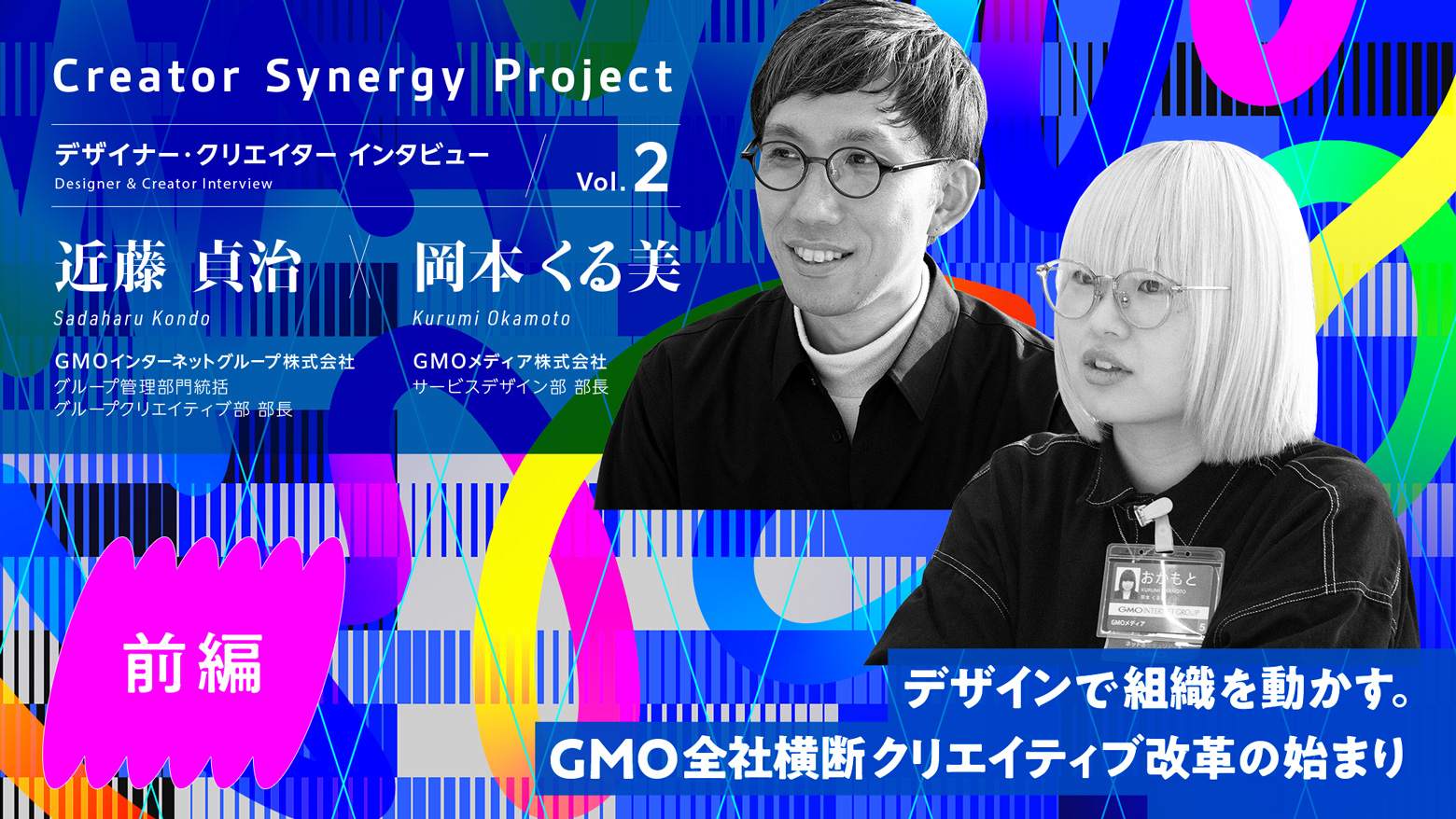
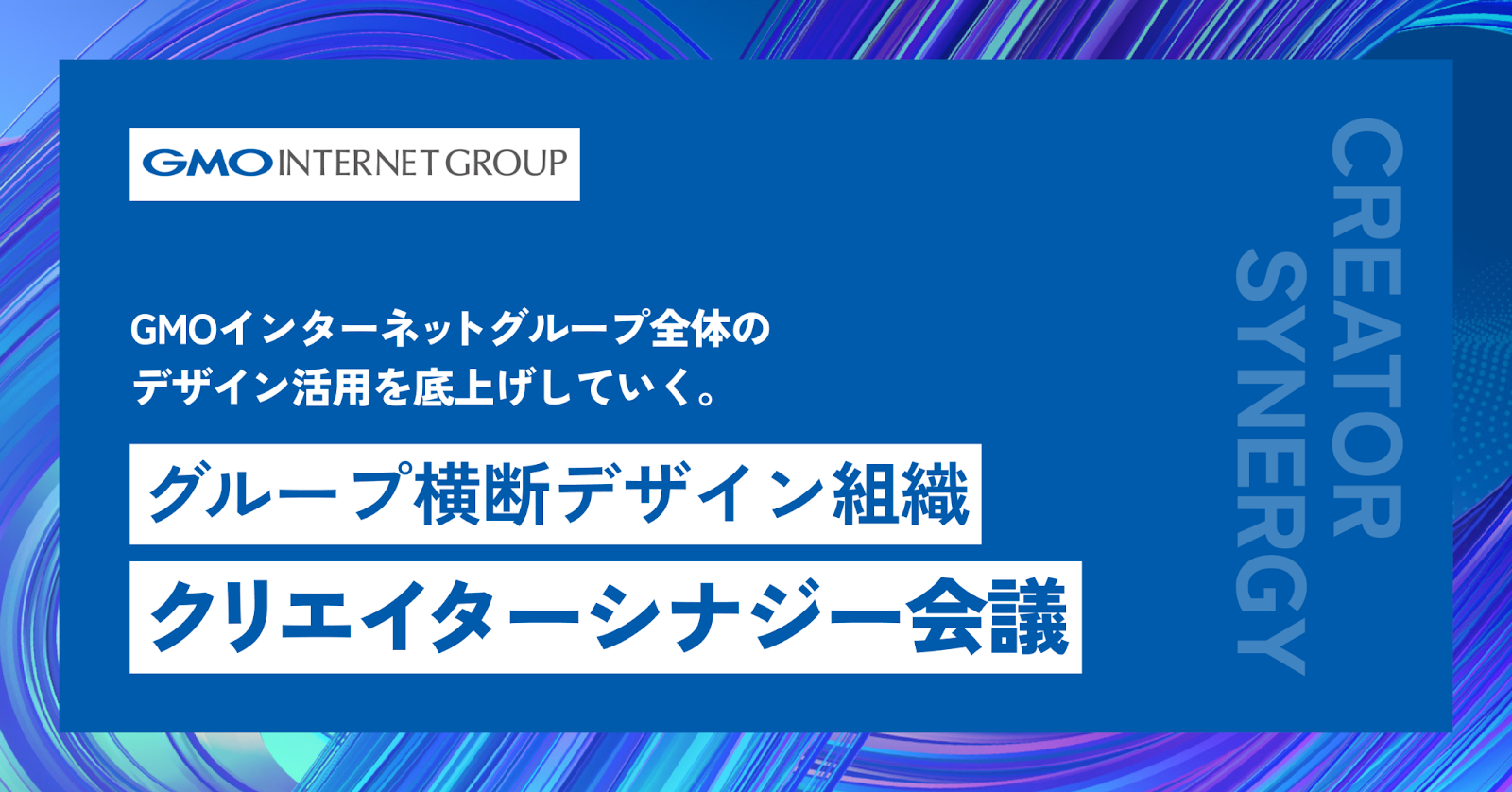
ブログの著者欄
採用情報
関連記事
KEYWORD
CATEGORY
-
技術情報(562)
-
イベント(209)
-
カルチャー(54)
-
デザイン(54)
-
インターンシップ(2)
TAG
- "eVTOL"
- "Japan Drone"
- "ロボティクス"
- "空飛ぶクルマ"
- 5G
- Adam byGMO
- AdventCalender
- AGI
- AI
- AI 機械学習強化学習
- AIエージェント
- AI人財
- AMD
- APT攻撃
- AWX
- BIT VALLEY
- Blade
- blockchain
- Canva
- ChatGPT
- ChatGPT Team
- Claude Team
- cloudflare
- cloudnative
- CloudStack
- CM
- CNDO
- CNDT
- CODEBLUE
- CODEGYM Academy
- ConoHa
- ConoHa、Dify
- CS
- CSS
- CTF
- DC
- design
- Designship
- Desiner
- DeveloperExper
- DeveloperExpert
- DevRel
- DevSecOpsThon
- DiceCTF
- Dify
- DNS
- Docker
- DTF
- Excel
- Expert
- Experts
- Felo
- GitLab
- GMO AIR
- GMO AIロボティクス大会議&表彰式
- GMO DESIGN AWARD
- GMO Developers Day
- GMO Developers Night
- GMO Developers ブログ
- GMO Flatt Security
- GMO GPUクラウド
- GMO Hacking Night
- GMO kitaQ
- GMO SONIC
- GMOアドパートナーズ
- GMOアドマーケティング
- GMOイエラエ
- GMOインターネット
- GMOインターネットグループ
- GMOクラウド]
- GMOグローバルサイン
- GMOコネクト
- GMOサイバーセキュリティbyイエラエ
- GMOサイバーセキュリティ大会議
- GMOサイバーセキュリティ大会議&表彰式
- GMOソリューションパートナー
- GMOデジキッズ
- GMOブランドセキュリティ
- GMOペイメントゲートウェイ
- GMOペパボ
- GMOメディア
- GMOリサーチ
- GMO大会議
- Go
- GPU
- GPUクラウド
- GTB
- Hardning
- Harvester
- HCI
- INCYBER Forum
- iOS
- IoT
- ISUCON
- JapanDrone
- Java
- JJUG
- K8s
- Kaigi on Rails
- Kids VALLEY
- KidsVALLEY
- Linux
- LLM
- MCP
- MetaMask
- MySQL
- NFT
- NVIDIA
- NW構成図
- NW設定
- Ollama
- OpenStack
- Perl
- perplexity
- PHP
- PHPcon
- PHPerKaigi
- PHPカンファレンス
- Python
- QUIC
- Rancher
- RPA
- Ruby
- Selenium
- Slack
- Slack活用
- Spectrum Tokyo Meetup
- splunk
- SRE
- sshd
- SSL
- Terraform
- TLS
- TypeScript
- UI/UX
- vibe
- VLAN
- VS Code
- Webアプリケーション
- WEBディレクター
- XSS
- アドベントカレンダー
- イベントレポート
- インターンシップ
- インハウス
- オブジェクト指向
- オンボーディング
- お名前.com
- カルチャー
- クリエイター
- クリエイティブ
- コーディング
- コンテナ
- サイバーセキュリティ
- サマーインターン
- システム研修
- スクラム
- スペシャリスト
- セキュリティ
- ソフトウェアテスト
- チームビルディング
- デザイナー
- デザイン
- テスト
- ドローン
- ネットのセキュリティもGMO
- ネットワーク
- ビジネス職
- ヒューマノイド
- ヒューマノイドロボット
- フィジカルAI
- プログラミング教育
- ブロックチェーン
- ベイズ統計学
- マイクロサービス
- マルチプレイ
- ミドルウェア
- モバイル
- ゆめみらいワーク
- リモートワーク
- レンタルサーバー
- ロボット
- 京大ミートアップ
- 人材派遣
- 出展レポート
- 動画
- 協賛レポート
- 基礎
- 多拠点開発
- 大学授業
- 宮崎オフィス
- 展示会
- 広告
- 強化学習
- 形
- 応用
- 情報伝達
- 技育プロジェクト
- 技術広報
- 技術書典
- 採用
- 採用サイトリニューアル
- 採用活動
- 新卒
- 新卒研修
- 日本科学未来館
- 映像
- 映像クリエイター
- 暗号
- 業務効率化
- 業務時間削減
- 機械学習
- 決済
- 物理暗号
- 生成AI
- 色
- 視覚暗号
- 開発生産性
- 開発生産性向上
- 階層ベイズ
- 高機能暗号
PICKUP