GMOインターネットグループが今年4月から開始する、年間を通してデザイン・クリエイティブの発信を強化する施策「Creator Synergy Project」の取り組みとして、本ブログでもデザイナー・クリエイターへのインタビュー連載をスタートしました!
[前編]「これが上場企業のクリエイティブ?」疑問から始まった、自走できるデザイナー組織づくりの旅に引き続き、今回は[後編]としてGMOインターネット クリエイティブ部の丸山清人さんが理想とする“提案できるデザイナー集団”についてお話を聞きました。
目次
キラキラの裏で思った。「現場が育ってなきゃ意味がない」
—エグゼクティブリードに就任されるまでには、どんな歩みがあったのでしょうか?

丸山
2013年の入社当初は「ConoHa byGMO」や「GMOアプリクラウド」のデザインを担当し、グラフィックや映像を中心に手がけていました。しかし、「お名前.com byGMO」のキャンペーンでビジュアルを担当したことをきっかけに、グループ横断の案件にも携わるようになったんです。「.shop」や「Z.com」のロゴ制作、GMOクリック証券の看板制作なども任せてもらえるようになり、いつの間にか「GMOインターネットグループ全体に関わるデザインの仕事をしている人」という立ち位置が定着していきました。
そうした取り組みを評価していただいた結果、当時のクリエイティブ職としては異例のスペシャリスト評価を受け、シニアデザイナーに昇格しました。
後進を育てる立場になったことで、プレイヤーとして手を動かすだけでなく、勉強会や講義を通じて自分の考えを言語化していくことを意識するようになりましたね。デザインにおける「質と量」の話を仲間に伝える時間も、自然と増えていったと思います。

丸山 清人|GMOインターネット株式会社 ドメイン・クラウド事業本部 クリエイティブ部 エグゼクティブリード
高校卒業後に米国サンディエゴへ留学。帰国後、テレビ業界でADを経験したのち、広告代理店にてデザイナー/アートディレクター/映像ディレクターとして活躍。GMOインターネット株式会社にジョイン後は、クリエイティブ部の育成指標の考案や体制構築を手がけながら、ドメインやレンタルサーバー・ホスティングなどインターネットインフラ事業のクリエイティブ監修を担う。加えて、セキュリティ関連のデザインや「GMO SONIC」などグループ横断プロジェクトにも幅広く関わる。

丸山
その延長線上で、アシスタントマネージャーという管理職に就くことになり、本格的に組織づくりにも関わるようになったんです。これにより、シニア時代から考えていたことを、新人研修の場などで話す機会も増えていきました。そして、プレイヤーとしての視点と、チーム全体を見る視点の両方を持ちながら取り組む中で、エグゼクティブデザイナー(アシスタントマネージャーと兼務)という役割を担うことになりました。
ところがその後、人事制度が大きく変わり、従来のスペシャリスト評価が廃止されることになりました。プレイヤーとして評価されるポジションがなくなるというのは、現場にとっても大きな転換点でしたね。そのタイミングで、改めて体制をどう設計するかを考えるようになり、現在の役職であるエグゼクティブリードを任されることになりました。
—丸山さんの存在感が増していく過程と並行して、GMOインターネットグループ全体としてもクリエイティブに力を入れていく方針が強まっていったと聞きました。

丸山
はい。ちょうど2023年ごろ、グループとしても「クリエイティブでNo.1を目指す」という方針が明確に打ち出されるようになっていったんです。その後押しもあり、2024年ごろからはデザインコンテスト『GMO DESIGN AWARD』の主催やデザインカンファレンス『Designship 2024』への出展・登壇など、社外に向けた取り組みや華やかな舞台が一気に増えていきました。
Designship 2024 協賛レポート[前編]/[後編]
ただ、個人的には、「このままでいいのかな」という葛藤もあって。

—というのは?

丸山
個人的には、“キラキラしたこと”をやるのは賛成で、デザイナーが自信をつけるための、貴重なアウトプットの場としてすごく前向きに捉えていました。ただ一方で、実態が伴っていないのに表面だけキラキラさせても意味がない、という冷静な自分もいて。


丸山
社外的にはデザインコンテストの主催やイベント協賛など華やかに見える活動をしていたとしても、制作現場が「カッコわるい」ままだと、本末転倒だなと。
やっぱり、まず大事なのは内側—つまり、良いクリエイターが育つ環境や、ちゃんと成長できる仕組みを整えること。それができて初めて、外に向けた活動が輝くんじゃないかと思ったんですね。
「No. 1になろう!」という動き自体はすごく嬉しいし、ありがたい。でもそれに甘えず、「自分たちがもっとちゃんとしなきゃ」と身が引き締まる思いでもありました。
—エグゼクティブリードとして組織を育てる立場だからこその危機感ですね。そこから少し時間が経った今も、同じ心境ですか?

丸山
そうですね。正直なところ、今もまだ「実態は完全には伴っていないな」と感じる部分はあります。
ただ、キラキラした舞台のおかげで、GMOインターネットグループのクリエイターにも、誇れることはあるんだと実感できる機会をいただけたことや、それを仲間と分かち合えたことには大変意味があったと思います。
グループの力で得られた機会を今後どうのように活かすべきか、今も試行錯誤中ですね。
自走するデザイナーをどう育てるか
—実際に現場をリードする立場として、今感じている課題は?

丸山
デザイナーとしての「こだわり」と「事業の成長」を両立させられるようなデザイナーの育成ですね。
正直なところ今もなお、昔ながらの組織構造が残っている部分もあるんです。つまり、「事業部がメインで、クリエイターはそのアシスタント」のような。クリエイターからの提案は業績が重要視されて、なかなか通らない場面もありました。
ビジネスの現場なので、もちろんその考え方は理解できます。ただ、「売れればなんでもいい」という姿勢を、そのまま受け入れるのはちょっと違いますよね。
デザインは本来、使う人にとってやさしく、わかりやすいものであるべき。僕はそういう信念を持っています。かといって、デザインの理想だけを追い求めて、「こっちのほうが美しい」と主張しても、それはそれで意味がない。結果として利益につながるものでなければ、それは“慈善事業”。僕たち自身も、生活が成り立たなくなってしまうんです。
ビジネスとデザイン。両者のバランスをどう取っていくのか。それを考え続ける姿勢こそ、これからのクリエイターに求められるものだと思います。要するに、「自分はクリエイターである前に、ひとりの事業会社の仲間なんだ」と誇りを持ち、その中で「自分に何ができるか?」を問い続けられる人。そういう人が、クリエイティブの力で事業に貢献できるんだと信じていますし、そんな仲間がもっと増えていくと嬉しいですね。

—そうしたデザイナーを育てるために、今はどのようなことに取り組んでいますか?

丸山
チームづくりにおいて大切にしているのは、まず「どこに向かうのか」を明確にすることです。基本的には、各チームのマネージャーとすり合わせながら、「今年はこういう方向性でいきましょう」と合意を取ることからスタートしています。
大枠では、昨年「2028年までに、どういうクリエイターでありたいか」という5年後のビジョンを掲げました。そこから逆算して、この1年に取り組むべき年次目標を設定。それをチームごとに共有し、チームとして何ができるかを話し合ってもらいます。そして最終的には、各メンバーの個人目標へとブレイクダウンしていく流れです。


丸山
たとえば、今年の重点テーマのひとつは「サービス課題に対する当事者意識とディレクション力の向上」です。
具体的には、「事業部の情報をもとに“お客様目線”で制作できるメンバーを○○%以上にする」や、「サービス成長に必要な情報技術を自ら収集・提案・制作できるメンバーを○○%以上にする」といった数値目標も設定しています。これは、“言われた通りに手を動かす”という従来型のスタイルから脱却し、“自ら提案できるデザイナー”を育てるための取り組みです。
もう一つ、重視しているのは「各サービスのブランドストーリーやカスタマージャーニーマップをビジュアル化する力」です。つまり、サービス課題を自分たちで見つけ、KPIを設定し、クリエイティブでどう解決していくかを自走して考えられるチームへの進化ですね。
こうした目標設定を通じて、将来的には、クリエイターが一定の裁量を持ってサービスを自らの手で高めていけるような状態を目指しています。事業部に任せきりにするのではなく、「この領域はクリエイティブが見ているから大丈夫」と胸を張れる状態が理想形です。
「誰かがやるべきなら、自分がやる」──たどり着いた管理職への道
—「いつまでも現場にいたい」と考えるクリエイターも多いなか、エグゼクティブリードとして奮闘し続けている理由は?

丸山
管理職というポジションに強く憧れていたかというと、正直、そうではなかったと思います。むしろ、自分の中に「こういうクリエイター組織であってほしい」という理想像があって、それを形にしていくうちに、結果的に今の役割に辿り着いたという感覚のほうが近いです。
本当は、誰か他にその役割を担ってくれる人がいれば、「じゃあ任せます」と譲っていたかもしれない。でも、誰もやらないなら、自分がやるしかない。そう思って自然と動き出したのが、マネジメントに関わるようになったきっかけでした。
「ここでやるべきことはすべてやりきった」と思えたときに、もしかしたら次のことを考えるのかもしれません。でも、まだ自分の中には“やるべきこと”が残っている。だからこそ、今もこの場所に立ち続けています。
理想は、“自分がいなくても回るチーム”。その未来をつくるために
—マルチタレントな丸山さんの、今の原動力は。

丸山
綺麗事に聞こえるかもしれないけれど、今でも僕の芯になっているのは、入社時から触れ続けている「スピリットベンチャー宣言」(GMOインターネットグループの企業理念)に掲げられたフィロソフィー。「お客様の「笑顔」「感動」を創造し、社会と人々に貢献する。」ことが使命だと考えているし、それを体現できるメンバーを増やしていけたら嬉しい。
話していて思い出したのですが、実は以前、チームの中で1人退職された方がいたんです。当時はまだ「Excelの仕様書をそのままデザイン」していた時代で、僕としてはじれったさがありながらも、「まあ、今は仕方ないよね」と、どこか淡々と受け止めてしまっていました。
でも、その方が退職する際に、「もっとデザインを教えて欲しかった」と言って去っていったんです。その言葉を聞いて初めて自分が、向上心があるデザイナーをみすみす逃してしまったことに気付きました。ああいう方がもう去って行かないような、そして、新たな仲間として入ってきてくれるような組織にすることが、管理者としての目標ですね。
強いデザインは、強い組織からしか生まれない。だからこそ、クリエイターが自分の意志で動き、事業に向き合える土壌をつくること。それもまた、クリエイティブの一部だと僕は思っています。「チームの一員として、何ができるか」を問いながら、クリエイターがもっと自由に、もっと主体的に動ける場所をつくる—それが、今の僕の役割です。

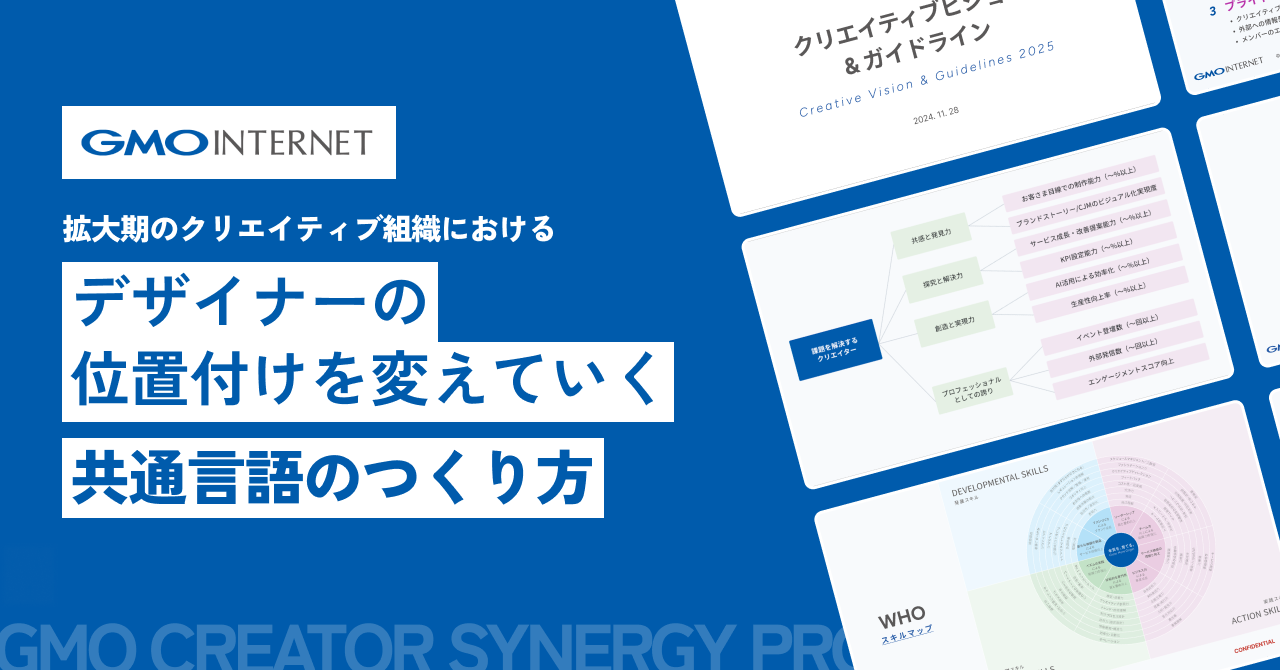
ブログの著者欄
採用情報
関連記事
KEYWORD
CATEGORY
-
技術情報(565)
-
イベント(211)
-
カルチャー(54)
-
デザイン(57)
-
インターンシップ(2)
TAG
- "eVTOL"
- "Japan Drone"
- "ロボティクス"
- "空飛ぶクルマ"
- 5G
- Adam byGMO
- AdventCalender
- AGI
- AI
- AI 機械学習強化学習
- AIエージェント
- AI人財
- AMD
- APT攻撃
- AWX
- BIT VALLEY
- Blade
- blockchain
- Canva
- ChatGPT
- ChatGPT Team
- Claude Team
- cloudflare
- cloudnative
- CloudStack
- CM
- CNDO
- CNDT
- CODEBLUE
- CODEGYM Academy
- ConoHa
- ConoHa、Dify
- CS
- CSS
- CTF
- DC
- design
- Designship
- Desiner
- DeveloperExper
- DeveloperExpert
- DevRel
- DevSecOpsThon
- DiceCTF
- Dify
- DNS
- Docker
- DTF
- Excel
- Expert
- Experts
- Felo
- GitLab
- GMO AIR
- GMO AIロボティクス大会議&表彰式
- GMO DESIGN AWARD
- GMO Developers Day
- GMO Developers Night
- GMO Developers ブログ
- GMO Flatt Security
- GMO GPUクラウド
- GMO Hacking Night
- GMO kitaQ
- GMO SONIC
- GMOアドパートナーズ
- GMOアドマーケティング
- GMOイエラエ
- GMOインターネット
- GMOインターネットグループ
- GMOクラウド]
- GMOグローバルサイン
- GMOコネクト
- GMOサイバーセキュリティbyイエラエ
- GMOサイバーセキュリティ大会議
- GMOサイバーセキュリティ大会議&表彰式
- GMOソリューションパートナー
- GMOデジキッズ
- GMOブランドセキュリティ
- GMOペイメントゲートウェイ
- GMOペパボ
- GMOメディア
- GMOリサーチ
- GMO大会議
- Go
- GPU
- GPUクラウド
- GTB
- Hardning
- Harvester
- HCI
- INCYBER Forum
- iOS
- IoT
- ISUCON
- JapanDrone
- Java
- JJUG
- K8s
- Kaigi on Rails
- Kids VALLEY
- KidsVALLEY
- Linux
- LLM
- MCP
- MetaMask
- MySQL
- NFT
- NVIDIA
- NW構成図
- NW設定
- Ollama
- OpenStack
- Perl
- perplexity
- PHP
- PHPcon
- PHPerKaigi
- PHPカンファレンス
- Python
- QUIC
- Rancher
- RPA
- Ruby
- Selenium
- Slack
- Slack活用
- Spectrum Tokyo Meetup
- splunk
- SRE
- sshd
- SSL
- Terraform
- TLS
- TypeScript
- UI/UX
- vibe
- VLAN
- VS Code
- Webアプリケーション
- WEBディレクター
- XSS
- アドベントカレンダー
- イベントレポート
- インターンシップ
- インハウス
- オブジェクト指向
- オンボーディング
- お名前.com
- カルチャー
- クリエイター
- クリエイティブ
- コーディング
- コンテナ
- サイバーセキュリティ
- サマーインターン
- システム研修
- スクラム
- スペシャリスト
- セキュリティ
- ソフトウェアテスト
- チームビルディング
- デザイナー
- デザイン
- テスト
- ドローン
- ネットのセキュリティもGMO
- ネットワーク
- ビジネス職
- ヒューマノイド
- ヒューマノイドロボット
- フィジカルAI
- プログラミング教育
- ブロックチェーン
- ベイズ統計学
- マイクロサービス
- マルチプレイ
- ミドルウェア
- モバイル
- ゆめみらいワーク
- リモートワーク
- レンタルサーバー
- ロボット
- 京大ミートアップ
- 人材派遣
- 出展レポート
- 動画
- 協賛レポート
- 基礎
- 多拠点開発
- 大学授業
- 宮崎オフィス
- 展示会
- 広告
- 強化学習
- 形
- 応用
- 情報伝達
- 技育プロジェクト
- 技術広報
- 技術書典
- 採用
- 採用サイトリニューアル
- 採用活動
- 新卒
- 新卒研修
- 日本科学未来館
- 映像
- 映像クリエイター
- 暗号
- 業務効率化
- 業務時間削減
- 機械学習
- 決済
- 物理暗号
- 生成AI
- 色
- 視覚暗号
- 開発生産性
- 開発生産性向上
- 階層ベイズ
- 高機能暗号
PICKUP
-

【協賛レポート|前編】日本最大級の学生向けAIキャリアフェス「AIチャレンジャーズフェス2025」
技術情報
-

【イベントレポート・後編】GMO Developers Day 2025 -Creators Night-|共創するデザイン組織と次世代クリエイターの可能性
デザイン
-

【イベントレポート・中編】GMO Developers Day 2025 -Creators Night-|変化に挑むクリエイターのキャリアと成長
デザイン
-

AI体験で地域をつなぐ──GMO hinata が挑むCSR活動最前線
技術情報
-

【イベントレポート・前編】GMO Developers Day 2025 -Creators Night-|AI時代の「クリエイティブ」を探る夜
デザイン
-

【イベントレポート】社内から未来を体験する-「ロボ触ろうぜ!」
技術情報




